船舶はこうして運河を通行する
** パナマ運河滞在記(2) **
| HOME | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 付記 |
第2部:ガツン・ロックに駐在して
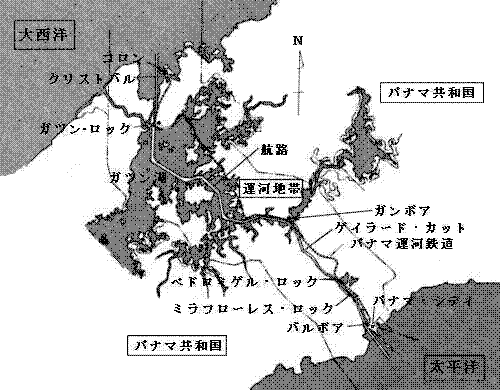 南北両大陸をむすぶパナマ地峡は地図上ではS字形に弧を描き、パナマ運河の水路は殆ど南北を向いています。北側が大西洋、南側が太平洋になります。太平洋から運河に入る船舶はまず、2段の水門堰があるミラフローレス・ロックを抜けて、ミラフローレス湖を横切り、1段のペドロミゲル・ロックでガツン湖水面の高さまで上昇します。
船は建設時最大の難所であった切り通し、ゲイラード・カットを航行したのち、さらにガツン湖を横切り、大西洋側のガツン・ロックで一気に3段の水門堰によって海面レベルに降下して大西洋に抜けます。この全行程はおよそ8時間ほどですが、そのうち3段のガツン・ロックの通過に40〜50分ほどかかります。
南北両大陸をむすぶパナマ地峡は地図上ではS字形に弧を描き、パナマ運河の水路は殆ど南北を向いています。北側が大西洋、南側が太平洋になります。太平洋から運河に入る船舶はまず、2段の水門堰があるミラフローレス・ロックを抜けて、ミラフローレス湖を横切り、1段のペドロミゲル・ロックでガツン湖水面の高さまで上昇します。
船は建設時最大の難所であった切り通し、ゲイラード・カットを航行したのち、さらにガツン湖を横切り、大西洋側のガツン・ロックで一気に3段の水門堰によって海面レベルに降下して大西洋に抜けます。この全行程はおよそ8時間ほどですが、そのうち3段のガツン・ロックの通過に40〜50分ほどかかります。
運河のロックには船を通す水路が2レーンあり、機関車が走る岸壁は中央がセンター・ウォール、東側がイースト・ウォール、西側がウェスト・ウォールと呼ばれています。ガツン湖と海水面との差約26メートルを3段の堰で水位調節するわけですから、各段は約8.5mの水位差になります。上段の水を下段に流して水位を合わせるため、あらかじめ下段の水位を下げておく必要があり、この場合水位差は17mになるので、長さ330m、幅34m、水位差17mとすると、この水位差で貯水された水の重さは約19万トンにもなります。この圧力を持ちこたえる水門のゲートは分厚く頑丈な鉄扉で、閉鎖時にはゲートの上は人の通路になっています。各ロックのゲート部両岸には50%(約26度)の急傾斜面があり、曳船機関車はこの勾配を登ったり降りたりします。それだけでなく機関車の重量は50トン強、船の大きさは大型船では6〜7万トン、引っ張り合いをしたら機関車の負けは明らかです。したがって滑らないようにラック・ドライブ(アプト式と同じ)であり、横向きに力がかかってもひっくり返らないようペアになった安全車輪で上部が拡がっているラックを両側から抱えるようにしてふんばります。

| |
|
| |
機関車と船とを結びつけるのは太さ1インチ(約2.5cm)のスチール・ワイヤー・ケーブルです。機関車には2台のウィンドラス(ウィンチとほぼ同じ)が載せられており、2本のケーブルで船と繋ぎます。船の大きさによって機関車は各岸に1〜4両、両岸で2〜8両が配置されます。このケーブルを介して牽引、ブレーキを働かせますが、停止中わずか数分間で水位を調節するため水室には大量の水が流れ込み、流れ出します。水路の下にはたくさんのバルブ(弁)があり、岸壁の地下には地下鉄のトンネルより大きいくらいの導水トンネルもあります。バルブを開いて上段の水を下段に流すのですが、この大量の水流でできる渦により船が動揺し、岸壁やゲートにぶつからないよう機関車はとまったままケーブルを介して強い力で船を押さえ込みます。このように停止中に大きな力を出せる装置としてこの機関車のウィンドラスは油圧駆動方式を採用しています。この機能は電気駆動では実現困難な能力で、容易な操作で自由にケーブルを操ることができる油圧駆動方式はこの機関車の最大の特徴と言えるものでしょう。両岸の複数の機関車は船に乗り込んでいる運河会社のパイロットからの無線指示で、力を合わせて船をコントロールするのです。(ここに記述している内容は2代目の旧型機関車のものですが、新型機関車も基本的には同じ構造で、新しい技術を盛り込んで高性能化、無保守化、ハイテク化を図ったものです。米国製初代機関車は両運転台型、電動ウィンドラス1台搭載でしたが、日本製の2,3代目は中央運転台型、油圧駆動ウィンドラス2台搭載という大きな違いがあります。)

| |
|
| |
1962年初頭からの試作車の現地試験は使用環境がもっとも厳しい3段のガツン・ロックで行われ、派遣技術者達はパナマ運河会社の社員アパートの1室を借りて、共同生活の根拠地としました。また問題発生時などときどき派遣された技術者の受け入れもしたので、我々はこの宿舎をガツン・ヒルトンのニックネームで呼んでいました。後の量産車納入時、契約に基づいて駐在した私を含めたサービス・エンジニアもこの宿舎を借りて住まいました。この宿舎はガツン・ロックから徒歩10分(近道すれば5分)くらいのところですが、食事に出たり他のロックに行くときは徒歩では無理なので中古車を手に入れて運転していました。
ガツンは大西洋側ですが、他のペドロミゲル・ロック、ミラフローレス・ロック、運河会社の管理部門の事務所・アドミニストレーション・ビルはいずれも太平洋側にありました。地峡の幅は約80km、週に何回も地峡横断道路(Trans-Isthmian Highway)を往復しました。(1999年、3代目の新型機関車は最初にミラフローレス・ロックに配備され、テストが行われました。)